宗教は「信じる」哲学は「考える」
最近、有名人が、宗教団体へ出家するため芸能界を引退するとの報道がありました。
昔読んだ本を再読しました。これです。
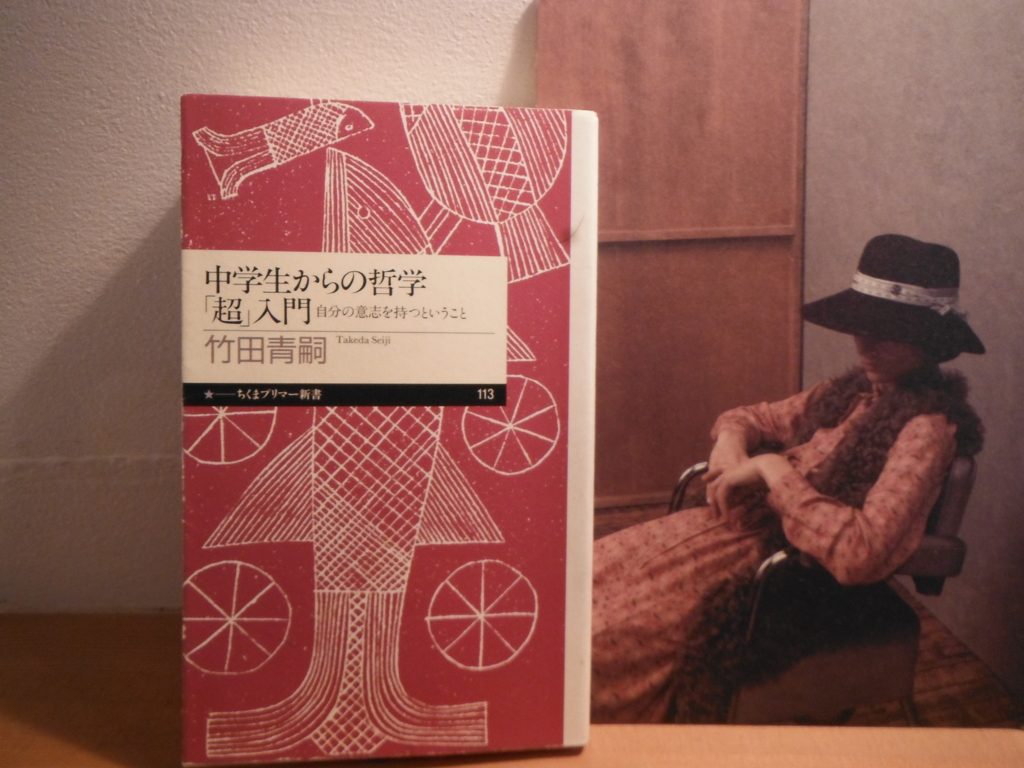
この本によると、動物は、食欲や性欲を満たすためだけに生きているけど、人間は自我をもっているため、
- 「我々はどこから来たのか」
- 「この世界はだれが作ったのか」
- 「何のために我々は生きているのだろうか」
というような根源的な問いを大昔からもっているのだそうです。
なるほど、確かにそうです。
宗教は、このような問いに答える形で生まれたと言います。
まず、一人の預言者が表れ、あれこれ変なことを言う。
でも、周りの人は、
「この人は奇妙なことも言うが、何か人間にとって大事なことを言っているぞ」
と思う。
そして、
「この人はきっと、人間が生きていく上で一番大事なものが何であるかを知っているに違いない」
という信憑がだんだん広がり、彼についていこうとするフォロワーが集まってくる。
こうして宗教が成立するのだそうです。
宗教には、まず、「教祖」がいて、皆が「この人は大事な真理を知っている」ということを信じていて、「教祖」が死んでも、「教祖の言葉」が残って、この言葉には「心理」が隠されていると信じて人が集まってくる。
そして、みんなでその言葉を解釈しながら、誰がそのその真理に一番近づけるのかを競い合う構造になっている。とのことです。
「教祖」の教義は基本的に「物語」の形をとっていて、
「神様がはじめに6日間で世界を創った」とか、
「宇宙では、太古以来、宇宙では光の神と闇の神が戦いを続けている」
という具合です。
宗教で大事な点は、
「この物語が果たして正しいかどうかは誰にも分らないが、それでもみんながそれを信じている」
ということです。宗教の特質は、世界を説明する聖人が存在し、みんなでその聖人を信じ、またその物語を信じるということで、そのことで、世界についての一つの共通理解が成り立ち、それが一つの共同体を作るうえで大事な役割を果たします。
一方、哲学は、原則的に「物語」という方法はとりません。
「概念」とか「原理」などの枠を使い、世界や万物などを論理的に説明します。
言うならば、
哲学とは、世界や人間の問題を、誰が最も巧みに説明できるか、という言語ゲーム
と言えそうです。
例えば、タレスという古代哲学者は、
「世界の森羅万象は「水」という最も単純な単位が集まってできている」
と言いました。
それに対して、その弟子は
「世界はこんなに多様なのに、水のような純粋なものからすべてができているとは思えない」
と言う。
それに対して、別の弟子が、
「水じゃない。空気だ」
と言います。
誰が正しいかはさておいて、このように自然の成り立ちを議論し説明し合うところから哲学はスタートしました。
宗教は教祖が作った物語を信じること、哲学はみんなで考えを出し合い言葉を探すこと、だそうです。
哲学から自然科学が生まれ、現代の科学が生まれています。理系の教科書に出てくるいろいろな説明は、真理というより、現時点ではこの説明が最も世界を合理的に表すことができるということなんですね。
大昔から皆悩んでいることは確か。そして、科学技術が発達した現代においても宗教はしっかりと社会に根を張っている。宗教がだめ、哲学(科学含め)がよし、とは思いません。この本を読んで、私は哲学や宗教、科学の成り立ちやその枠組みについて知ることができました。